[�߂�]
�@[�s�n�o]
�@[�s��]
�@[�V��]
�@[�m��]
�b�@�@���@�@���@�@�́@�@��
�@�b�����̕揊�́A
�@�@�E ����̎�/�����`�A���@(���݉ƁA����فA�O�Y����/���莛)
�@�@�E ���R�_�@(���c�R����)
�@�@�E �|�ޕ_�@(�ʏ�/�Ԍ����X�_��)
�@�@�E �K���X�_�@(�V�J��)
�@�@�E �p�ق��V�J��
�Ȃǂɂ���B
�@���c�R�̖k�[��т́A���R�_����|�ޕ_���܂߁A�b�����̕��ł������Ǝv����B
 �@400�N���������b������̎n�c�ł���B
�@400�N���������b������̎n�c�ł���B
�@�O�Y���`���̂V�j�Ƃ��āA�O�Y�����ł��鑊�͍��̍����Œa���B
�@�ۉ�4(1138)�N�̒a�������L�́B
�@�����i���{��s�����j������\���A�������𖼏��B
�@����4(1180)�N�̌����������ɁA�ꑰ�Ƌ��ɒy���Q���Č�Ɛl�ƂȂ�B
�@��m�J�̍���ł͌��`�o�̌R�ɑ����A"�t���Ƃ�"�Ő^����ɋ삯���蕐���������Ă���B
�@���B�����ł̌��������A��Îl�S��q�̂���B
�@���v2(1191)�N�A�n���Ƃ��ď��߂ĉ�Ó��肵���̓�����w���Ƃ����B
�@���̌�A���݉Ƒ��̍��{�Ɋق�z���A�ڂ�Z�ށB
�@���������������b�����𖼏��A�L�͂Ȑ퍑�喼�Ƃ���400�N�̉h���ւ邱�ƂɂȂ�B
�@��������ɂ́A���s�}���O�Ƃ��āA������u��Î��v�Ə̂���قǂɂȂ����B
 �@�傤�́A�i�m6(1298)�N�Ɍ����B
�@�傤�́A�i�m6(1298)�N�Ɍ����B
�@�����`�A���̕�́A���݉� (�傤��) �̑��ɁA
�@�@�@�E�ݏ�̊���� (�ܗ֓�)
�@�@�@�E�O�Y�����̍��������莛 (�ܗ֓�)
��3�J���ɂ���B
| �@ |
�@���i20(1643)�N�A�ۉȐ��V�������K�˂�B
�@����8(1668)�N�A���V�����R��ō��ɖ����������J�n�����B
�@���\8(1695)�N�A�R��/�������e������̘e�ɔ蕶�Ȃǂ����������B
�u������`�A���v
|

|
| �@ |
�@���̔ˎ�͋߂���ʂ�ۂɗ�������Ă���B
�@�@�E����10(1725)�N�A���e��
�@�@�E���a2(1765)�N�A���a6(1769)�N�A���i4(1775)�N�A�����e���
�@�@�E����11(1799)�N�A�����e�Z�� (��N�̎�)
�@��(�쑽���s�M�����[������)
�@�@��
�@��
�@[�Ð}]
|
����� (���킨����)

�@��(1247)�N�A�R���̎x��Ƃ��ĉ��[�������쐼���̔䍂�P�O���[�g���قǂ̒i�u��ɒz�����Ɠ`���B
�@����5(1189)�N�A�����`�A���̎w���ō������^���z�����Ƃ��B
�@���i9(1402)�N�A�V���q����F���ꑰ�̐V�{��V�{���Y���r�ɍU�߂��ŖS���A����ق��p�قɂȂ����Ƃ����B
�@���݂͑�n�ɂȂ��Ă��邪�A�k���̎�{�����{�̎Вn��A���q�������א_��/�쑤�Q���̗����Ȃǂ��ق̓y�ۂ̐ՂƂ����B

�@���q���Δ�̂ق���s�Ղɐ���̌ܗ֓����������A�y�ۂ̖k�[�ɋʉ� (�� �쉮) �ƌ����n�������邱�Ƃ���A�̎�̕�Ƃ��`�����Ă���B
�@��(�쑽���s�M�����[���{�쎚����`�������c)
�@[�Ð}]
�|�@�@�ށ@�@�_�@�i�Ԍ����X�_)


�@���̗̂R���́A16��/��������恂̒��ɂ���u�|�ށv�ɂ��B
�@�l������傫�Ȑ쌴�ɂ���B
�@��̏�ɂ́A�ܗ֓������Ă��Ă���B
�@�ܗ֓��́A�ۉȐ��V��������5(1665)�N�Ɍ����B�@�@�@�E�E�E�@�u��ÔˉƐ����I�v����
�@10��/���v���ƁA12��/���F������19��/�������܂ł̕揊�Ƃ����Ă���B
�@16��/�������E17��/�������E18��/�������̂R��ȊO�́A��傪����ł��Ă��Ȃ��B
�@18��̓��ׂ�ɂ���͂��́A19��/�������̕���������Ă��Ȃ��B

 �b�� ���� (���肤��)��
�b�� ���� (���肤��)��
�@�@��P�U��̎�
�@�@�����̒��a11.6���[�g���A
�@����3���[�g���̉~�`��

 �b�� ���� (���肨��)��
�b�� ���� (���肨��)��
�@�@��P�V��̎�
�@�@�����̉~�`��
�@�@��/����������ɖS���Ȃ�

 �b�� ���� (���肽��)��
�b�� ���� (���肽��)��
�@�@��P�W��̎�
�@�@�����̉~�`��
�@���a6(1620)�N�A�ٛ�������a�����r�p���Ă����@�p�������߂ĊJ�R���A16�`18��̕�Ƃ��čċ������B

�@�k�ɖ�50���[�g���ɂ��A13��/��������14��/�������Ƃ�����������邪�A�唼�͏Z��n�ɂȂ��Ă���B
�@(���L�n)
�@��(��Îᏼ�s��c���厚���⎚�Ԍ���u76�|2)
���@�@�@�@�R�@�@�@�@�_
�@���c�R�̒����ɂ���B
�@���̗̂R���́A�R��/��������恂̒��ɂ���u���R�v�ɂ��ȂށB
�@����������X��/�������܂ł̕_���Ɠ`�����邪�A�e�̎�̕�n�͓���ł��Ă��Ȃ��B
�@�u�������������V�}�v�ŁA��ώ������̎R�[�ɕ`����Ă���B
�@[�j��]
�@[����/�z�u�}]
�@�V��/�������܂ł́A�唼�����q�⋞�s�ɋ��Z���Ă����悤�ŁA��������i��������Ƃ����Ă���B
�@��(��Îᏼ�s��c�������R��460-1)

�@�b����/���R�i���ゴ��j�_ (��)

�@�V��/����������W��/�F�����܂ł̕_���Ɠ`������B
�@�u�������������V�}�v�ŁA��ώ������̎R�[�ɕ`����Ă���B
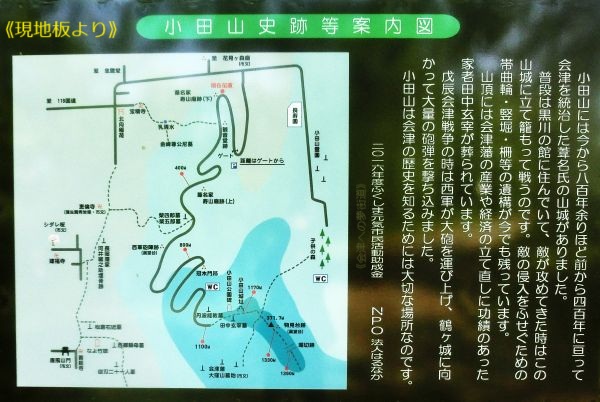

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
| �@ |
 ���R�_(��)�@������260��
���R�_(��)�@������260��
���R�C�w��(�W�]��)�@������435��
�b�ώ��ւ̕����ꓹ�@������360��
�O�H�\���E�c�����ɂ̕�@������1040��
���c�R�隬(�R��)�@������1060��
�v.�b�@������260��
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
 �@�ω�����
�@�ω�����
 �@���a3(1354)�N�A���J��O���o�����ω����̗y�q���Ƃ��đn���B
�@���a3(1354)�N�A���J��O���o�����ω����̗y�q���Ƃ��đn���B
�@��C�̖������R�ɏĂ������Ă��܂����B
�@�@�� �N�/�V��5(1379)�N�A�b������������/���J��O��
�@�@�@�@���{���邽�߁A����J��Ƃ�����ώ����ቺ�ɑn���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�b����/���R�i���ゴ��j�_ (��)
 �@�R��/�������i���R���j����U��/�������܂ł̕_���Ɠ`������B
�@�R��/�������i���R���j����U��/�������܂ł̕_���Ɠ`������B
�@�u�������������V�}�v�ŁA��ώ������̎R�[�ɕ`����Ă���B
����������T�� (���J��O) �̕�



�@�V��̎�/�b���������̕ꓰ/���J��O (��ώ��a����������T���) �̕�Ɠ`���B
�@�����P.5���[�g���A���S���[�g���̒ˁB
�@�ω����Ղ��牺��~�肽��ώ��̗���A�������̋߂��ɂ���B
�K�@�@���@�@�X�@�@�_
(��������)�@���J��c��Y ���A�@�I��p�Y ���@�@�@.
 �@�����̕��̌`���Ƃ͖��炩�ɈقȂ��Ă���A�蕶�̍����Ȃǂ��m�F�ł��Ȃ����A�����ɕ`���ꂽ�u�@���揊�}�v�Ȃǂ���A11��̎�/�b�����M���̕�Ɛ��肳���Ƃ̂��ƁB
�@�����̕��̌`���Ƃ͖��炩�ɈقȂ��Ă���A�蕶�̍����Ȃǂ��m�F�ł��Ȃ����A�����ɕ`���ꂽ�u�@���揊�}�v�Ȃǂ���A11��̎�/�b�����M���̕�Ɛ��肳���Ƃ̂��ƁB
�@��ɁA�Č����ꂽ��肩�B
�@���͂����͂ނ悤�ɁA��i�����Ί_���c�����Ă���B
�@�V�J���̓��̗��R/�V�J�W�����̏������ʒu�ɂ���B
�@�V�J���́A���M�����n�������B
�@��(��Îᏼ�s���R���厚�ΎR���V�J)
���@�́@���@�́@��

�@�ɒB�R�Ƃ����㌴�̐킢�Ŕs�ꂽ20��/�`�L���́A�錧�]�ˍ�̍]�ˍ����o�āA�H�c�Ɉڕ������B
�@��Â��V�J���̖����Ƃ��āA�܂����������̎R���E�������V�J�����A�ԏ�R�̘[�ɕ�Ƃ��đn�����Ă���B
�@�b���ƕ_�������邪�A�R��œr�₦���B
�@��(�H�c����k�s�p�ْ���V��10�@Tel. 0187-53-2904)
[�߂�]
�@[�s�n�o]
�@[�s��]
�@[�V��]
�@[�m��]